おぶせオープンガーデンとは
About
About
おぶせオープンガーデンとは
オープンガーデンとは個人の庭などを一般の方に公開する活動のことです。1927年にイギリスで創立されたNGS(ナショナル・ガーデン・スキーム)という善意団体が、個人の庭園などを一般の方々に公開し、それに関わる収益を看護・医療などに寄付した活動が、オープンガーデンの始まりと言われています。
おぶせオープンガーデンは、2000(平成12)年に38軒でスタートしました。これは、1980(昭和55)年から取り組んできた「花のまちづくり」、また、小布施町に伝わる「縁側文化」「お庭ごめん」の相乗効果として、訪れた方々を花でもてなし、会話を通して交流を図るもので、官民が一体となって取り組んだオープンガーデンとしては全国初となっています。
小布施町のオープンガーデンは「外はみんなのもの、内は自分たちのもの」という概念のもと庭の規模や質などを問わず誰でも参加できます。「『ガーデン』よりも『オープン』」が小布施町のオープンガーデンです。

案内板は「どうぞお入りください」の目印。
自由にお庭を鑑賞できます
おぶせオープンガーデンの看板があるお庭であれば自由に出入り可能です。
最初はお庭に入るのに戸惑ってしまうかもしれませんが、この案内板は「どうぞお入りください」の目印。ぜひ、お庭をお楽しみください。
Obuse Open Garden Book
おぶせオープンガーデンブック
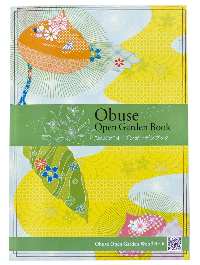
おぶせオープンガーデンブック
¥100(税込)
おぶせオープンガーデンに登録されたお庭の情報が詰まった一冊です。
お庭の写真や、オススメの季節、お庭に咲く花の種類など、お庭に関するの情報はもちろんのこと、オーナーがどのような想いを込めてお庭を作っているかも知ることができます。ぜひ一冊お手元にどうぞ。
「おぶせオープンガーデンブック」は次の施設でお求めになれます。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 小布施総合案内所 (小布施文化観光協会) |
小布施町大字小布施1497-2 (小布施駅舎内) |
026-214-6300 |
| 小布施ガイドセンター(ア・ラ・小布施) | 小布施町大字小布施789 | 026-247-5050 |
| 町営松村駐車場 | 小布施町大字中松36-1 | 026-247-5168 |
| 町営森の駐車場 | 小布施町大字小布施157-3 | 026-247-6572 |
| フローラルガーデンおぶせ | 小布施町大字中松506-1 | 026-247-5487 |
| 高井鴻山記念館 | 小布施町大字小布施805-1 | 026-247-4049 |
| おぶせミュージアム・中島千波館 | 小布施町大字小布施595 | 026-247-6111 |
| 道の駅オアシスおぶせ | 小布施町大字大島601 | 026-251-4111 |
| 小布施町役場 産業振興課 | 小布施町大字小布施1491-2 | 026-214-9104 |
郵送をご希望の方
お問い合わせフォームかお電話にて(小布施町役場産業振興課商工振興係:026-214-9104)お申し込みください。
Greeting
ごあいさつ
「おもてなし」
それが、
おぶせオープンガーデンの
キーワードです。
おもてなしの心を「オープンガーデン」に託して
小布施町長 大 宮 透
栗と北斎と花のまち 小布施町は、長野県の北東部に位置する人口が約11,000人の県内で最も面積が小さな町であります。町の特産品である栗は600年以上の歴史があるといわれ、江戸時代には幕府への献上品であったことから広く知れ渡るようになり栗の名産地となりました。江戸の浮世絵師である葛飾北斎も小布施町に招かれ、小布施町を大変気に入り、祭り屋台をはじめ多くの肉筆画を遺しています。
昭和56年~62年にかけて町中心部周辺を修景、整備する『町並み修景事業』が行政と関係住民・事業者の協働によって行われ、周辺住民・企業による格調ある住まいづくり、店舗づくりが進み、個性をもった新しい町並み景観が形成されてきました。古いものを生かしながら現代の生活にあった暮らしを実現し、住む人・訪れる人が心地よく過ごせる町並み空間が形成されることで、私たち小布施人(おぶせびと)は「景観」に寄せる思いが強いものになっていき、「内は自分のもの、外はみんなのもの」のコンセプトが小布施町全体に浸透していったのです。
「景観」に歩調を合わせるように各家庭では日常生活に『花』を取り入れ、豊かな生活空間を形成し、さらには丹精込めた庭をお客様にご覧いただき、花を通した交流による心のつながりを目指して始められたのが小布施町のオープンガーデンです。小布施町に古くから伝わる「お庭ごめん」の縁側文化を現代風に解釈した取組でもあり、「交流」と「協働」を大切にしてきた小布施を象徴するものであると自負しています。
オープンガーデンを通じて、ご来町いただいた皆様と小布施人との豊かな交流が生まれること、小布施町が大切にしてきた思いを少しでも感じていただくことができれば幸いです。多くの皆様のご来町を、心よりお待ち申し上げます。
おぶせオープンガーデンの「おもてなし」
元ガーデニング大楽校副校長 鷲尾 金弥
30年余の歴史を持つ小布施町の花のまちづくりのなかで、オープンガーデン発祥以来のテーマは『おもてなし』であります。全国的に大流行したオープンガーデンでしたが、そのほとんどが出展参加者の庭のデザイン技術やできばえを競うコンテストであったように思えます。このようなオープンガーデンが次第に顧みられなくなったことは当然の成り行きと申せましょう。
そういう世間の流れの中で、変わらずに盛んなおぶせオープンガーデンは町の人々の丹精込めた花づくり、庭づくりを通じての、来訪者の皆さんへの変わることのない『おもてなし』がその神髄であります。小布施にご来訪の折は、ぜひともオープンガーデンを訪れ、町の方々の心からの『おもてなし』を味わっていただきたいと思う次第です。
[プロフィール]
米国での観葉植物の生産販売会社などを経て、(有)ワシオアソシエイツを設立。花をテーマとした空間デザイン、大規模なフローラルデザイン、花博、フラワーショーのプロデュースや、新品種を海外より導入し普及を図るなど、造園や園芸の分野で関与され、「2000年兵庫県淡路花博ジャパンフローラ」では花卉(かき)修景プロデューサー英国王立園芸協会日本支部顧問などを勤めた。